
医療法人社団 高邦会 高木病院 https://takagi.kouhoukai.or.jp/
永沢 善三 先生 医療法人社団 高邦会 高木病院(前高邦会グループ病院 検査技術部長)国際医療福祉大学大学院 保健医療学専攻 臨床検査学分野 特任教授
■取材前記
福岡県南部に位置し、古くからの伝統工芸で発展してきた大川市。地域の中核病院として、国際医療福祉大学関連施設でもある高木病院は、救急医療から在宅医療までを担う、地域になくてはならない病院である。今回は同病院の「臨床微生物遺伝子検査研究センター」立ち上げに尽力された感染制御分野の重鎮 永沢氏と、院内のICT メンバーの皆さんに話を伺った。

左上より
薬剤部 濱田 浩平様/検査技術部 室長 寺﨑 裕子様/看護部 米倉 由規様/看護部 副師長 中野 晴佳様/事務部 課長代理 千倉 里美様
左下より
薬剤部 部長 西村 信弘様/医局 副院長 呼吸器内科部長 川浦 太様/看護部 副師長 田嶋 梢様/検査技術部 成田 妙子様
■地域および病院の特徴
永沢:大川市は古くから木工産業、特に家具の加工で栄えた土地です。大きな運河があり、九州各地から運ばれた木材を大川で加工し、港から日本中に送ることができるため、多くの職人が集まったと聞いています。「大川家具」といういわゆる高級な家具ですね。しかし市内には鉄道が通っていないため、交通の便に問題があり、また残念ながら高齢化も進んでいます。
一方で、高木病院の理事長が栃木県に開学した「国際医療福祉大学」は現在、全国に6つのキャンパスがあり、そのうちの大川キャンパスが当院に隣接していることから、当院は国際医療福祉大学の関連施設という役割も担います。大学では海外からの留学生も受け入れており、医師としてのトレーニング後は自国での大病院のトップや大臣になるような人材を育成しています。
高木病院でも他地域からの医学実習生も受け入れています。すぐ隣に大川キャンパスがあり、医師・薬剤師・検査技師・看護師・リハビリテーション関連など多くの学生が臨床実習を受ける病院でもあります。
千倉:当院は大川地区だけではなく、南筑後地区、福岡県南部の中でも中心的な地域医療に貢献している病院で、年間3,000台の救急を受け入れております。病床数は506 床を擁し、急性期・療養型・地域包括ケアの各病棟を備える病院です。一次、二次救急から慢性期まで継続的な医療を提供する形で地域に貢献しています。総合病院ですので大学病院と遜色ない機能もありますし、昨年度はロボット手術も導入しています。この地域にはなくてはならない病院です。
■微生物検査室の立ち上げ
永沢:2013年に国際医療福祉大学として、初めて臨床検査技師を養成する学科を、この大川キャンパス(福岡保健医療学部)に立ち上げました。臨床検査技師の養成には3年時に臨地実習が必要になってきますが、残念ながら以前の高木病院では微生物検査を外注に出していたので、臨床検査学科の学生が実習できる場所がありませんでした。
そこで医学検査学科として、この高木病院の中に「臨床微生物・遺伝子検査研究センター」を立ち上げることになりました。立ち上げに際しては、私が以前佐賀大学医学部附属病院に勤めていましたので、国立の大学病院と同じようなレベルの微生物検査室を立ち上げたいという要望を病院側が受け入れてくれました。
■ICONS21導入の経緯
永沢:私が佐賀大学医学部附属病院に在籍していた時、佐賀大学医学部附属病院は1998年に日本で初めての「総合感染症コントロールシステム」を立ち上げました。当時は医療の進歩に伴い、新生児・老人・胆がん患者等の重症患者の増加、あるいは免疫療法や放射線療法等による未感染状態の患者さんが増加していた頃です。さらにはMRSA などの多剤耐性菌の流行など、感染症を巡る問題は重大かつ多彩でしたが、これに的確に対応するシステムは実現されていなかったという背景があります。
そこで当時の只野壽太郎検査部長が大きな予算を獲得され、医療側とシステム企業が共同でまったく新しいシステム「Dr.FLEMING; ドクター・フレミング」を作り上げた、ということです。MRSA をはじめとする院内感染が蔓延し、耐性菌も多種多様になってきたため、院内感染の発生状況をリアルタイムでチェックするようなシステムが必要になっていました。
一方、日本の医学部では臨床細菌学の系統的知識はあくまで卒後教育に任されていました。さらに健康保険の出来高払い制により高価な薬剤の使用が増加し、国家財政を圧迫していたため、感染症専門医に代わるシステムを作ろうという構想にて、ケーディーアイコンズの技術者にも協力していただき「Dr.FLEMING」を作り上げました。
そして2013年の「臨床微生物・遺伝子検査研究センター」の立ち上げの際に、「Dr.FLEMING」の機能を引き継いでより進化した、ICONS21を導入し、検査のみならず、診療支援情報ともリンクして感染制御等のシステムにも貢献できるようになりました。「Dr.FLEMING」では、日本で初めてグラム染色など特殊染色の画像撮影を行いました。その画像も ICONS21に導入していただき、今でも血液培養をはじめ喀痰などのグラム染色像はすべて撮影し保存されています。この画像情報は日常診療でいつでも閲覧できるため、臨床医にとっては大きなメリットとなっています。
■院内における感染制御 ―ICTの活動―
田 嶋:2006 年 にICC (感染対策委員会)が発足、その後2013年4月にICT が設置されました。ICT の役割は大きく5つあります。
①感染状況の把握と指導を目的とした院内ラウンド
②抗菌薬の適正使用の推進
③職員研修の実施
④感染対策マニュアルの作成と見直し、遵守状況の把握
⑤サーベイランスの実施( 医療器具関連サーベイランス・手指衛生サーベイランス・薬剤耐性菌サーベイランスなど)
毎週火曜日16時から、常勤医師1名、感染管理認定看護師(CNIC)2名、専任の検査技師1名、専任の薬剤師1名で院内ラウンドを実施しています。患者さんやご家族、病院職員など、病院内すべての人を感染から守るという目的の下、感染防止対策の実践確認と評価を行い、感染防止対策のさらなる充実を目指しています。また、各職種が専門的な知識・技術・経験を用いて、問題となる感染症の発生状況を把握し、根拠に基づいた感染防止対策を実践できるように組織横断的に活動しています。 また、血液培養での陽性結果や耐性菌検出時には、状況に応じて速やかに報告を行います。
<それぞれの役割>
川浦:私は感染対策委員長として、現場のスタッフ(看護師や技師など)の意見や現場での課題を集約し、病院の執行部や医師に共有しています。また、必要に応じて執行部の方針や対策内容を現場にフィードバックするなど、双方向の意見交換を行なっています。また、 ICT メンバーと協力して手洗いなどの教育を行っています。院内でアウトブレイクが発生した場合には、具体的な治療法などについて、医師からの相談も受け付けます。現在は、抗菌薬の使用に関する相談や、新型コロナウイルス感染症が重症化した場合の対応に関する相談なども受け入れられる体制を整えています。
また、ICT 以外にもAST での活動も行っており、薬剤を中心に病院全体で適正使用が行われているかを確認し、主治医にフィードバックする役割も担います。例えば血液培養で陽性が出たら検査部から報告が届くので、耐性菌に適する薬剤について薬剤部と検討します。また、グラム染色で陽性がでたらどのような菌が考えられるかを検査部に問い合わせます。
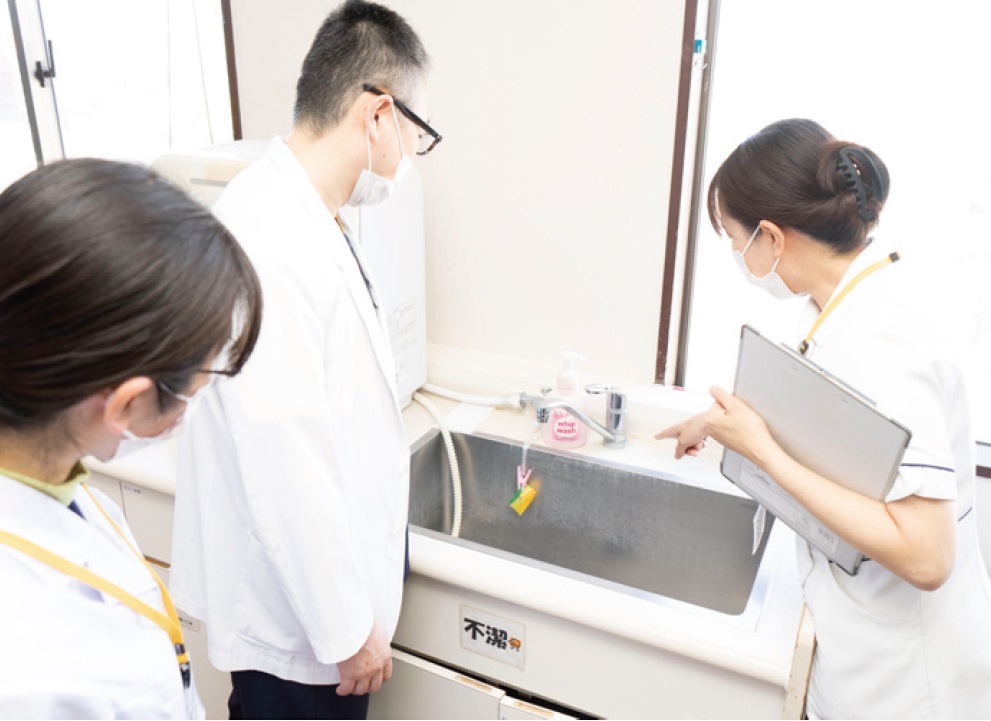
田嶋:看護師は各部署に感染対策委員が 1名おり(院内全体で22名)、月に1回の委員会でICT ラウンドの結果を共有し、改善策などを話し合っています。例えば、 ICT ラウンドにより複数の部署で同じような箇所での環境感染の指摘を受けたら、看護部全体としての対策を話し合うこともあります。
濱田:抗菌薬と消毒薬については薬剤師が関わることが大きいです。診療方針にも基準はありますが、そこから脱線しない範囲でモニタリングしながら、抗菌薬の適正使用を推進しています。
成田:臨床検査部では細菌検査の結果をお伝えするとともに、問い合わせにも対応します。感受性試験が必要なものが検出された場合もお伝えし、必要に応じて試験を行っています。
西村:AST に関しては薬剤師主導で症例カンファレンスを定期的に行っていますが、そのための資料作りは薬剤師が担当します。主にターゲットとしているのは耐性菌治療薬、特に MRSA 治療薬を使用している患者をピックアップし、ICONS 21 で微生物検査状況・検出状況などを資料化しています。

■チーム医療とICONS21
川浦:医師の視点ですと、グラム染色の結果などをその日のうちに画像でパッと出て確認できるのは良いですよね。1日に何十人分もの検体検査を依頼しますが、「この菌に対してできる治療」に早く対応できるようになっているのは助かります。培養試験は結果が来るまで時間がかかりますが、まずは画像を見ることでエンピリック治療を始められるので、治療に差が出てきます。
田嶋:医療器具関連サーベイランスに関するデータの収集にはすごく役立っています。また、毎月各部署から上がってくる感染者の報告(耐性菌はMRSA、ESBL、CRE の3菌種)をもとに、どのような感染対策が行われているかを各部署の看護師(委員)と現場に行って確認します。各部署のスタッフもICONS21を使ってすぐにデータを出し、利用しています。
成田:検査結果を画像でも示すことができるため、所見が治療の根拠として役立てていただけると思います。集計機能をよく使いますが、耐性菌に対するアンチバイオプランを薬剤師に報告することもできます。
■現在の課題と、 ICONS21への期待
川浦:現在はPC の前に来ないとICON S21が操作できないのが難点かもしれません。状況によってはタブレットで直接情報を確認しながらICT ラウンドを行った方がより効果的というシーンもあります。今後はタブレットでの利用も検討したいです。
田嶋:ICT ラウンド中にタブレットで撮影した写真もデータとして利用し報告書を作成する、というのが理想です。それから少し視点は変わりますが、「今ここにいる患者さんは以前どこの病棟にいたか」という履歴が分かると助かります。同じ病棟から同じ菌が出たときなどその広がりを見たい場合があります。
当院は急性期から慢性期までのケアミックスの病院のため、病棟の移動はよくあります。以前の病棟で感染症の発生があった患者さんは今どこにいるかというのも、病院全体での感染の広がりを見るには有用な情報です。
西村:薬剤師の視点では、医薬品のマスターのメンテナンスを進める必要がありますので、標準医薬品マスターなどとリンクできると良いと思います。また薬剤師はAST で関わることが多いのですが、どの病棟でどの抗菌薬がどれくらいの期間使われているかといった情報も、 ICONS21から確認できると助かります。
永沢:現在のところ、病院全体としては使い切れていない部分があると思います。使う人は頻繁に使うものの、必要性を感じなければ使う機会は少ないのが現状でしょうか。 しかし、ICONS21の機能を知って使いこなせれば、感染制御の非常に強い味方になります。今後はタブレットの利用も検討しながら、院内での利用を徹底できればと考えています。
■編集後記
感染制御分野のレジェンドとも称される永沢氏と、院内の感染制御に真摯に取り組むICT チームのみなさん。数多の医療人を排出する大学の関連施設において、幅広い分野で地域に貢献するという重要な役割も担っている。そんな彼らの傍らで「安全な医療の提供」をともに目指す ICONS21は、これからも時代の流れに合わせたさらなる進化を遂げていくことだろう。
※上記記事は全て取材当時のままを掲載
